ありがとう、そしてさよなら、6年生!(はじめての公立小)
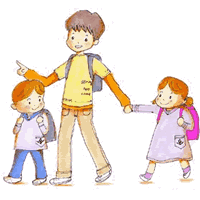
不安だらけの公立小学校を「もしかしたら大丈夫かも知れない」、と思わせてくれたのは、我が子の手を引いて校内を案内してくれた6年生だった。学校行事のリーダーとなり、町で会えば声をかけてくれた頼もしい6年生たち。かれらが今、巣立っていく...
「あのね、今度、僕たち6年生にね、『あり~がとう、さよ~なら年長さ~ん♪』(「ありがとう、さようなら」)の歌あるでしょ。あれ歌うんだよ」と、ある日、帰宅するなりわが息子。
「ああ、去年、幼稚園の卒園式で年中さんたちに歌ってもらった曲?」
「そうそう。だけどね、『年長さ~ん』を『ろ~くね~んせい(6年生)』に替えて歌うんだ。ほかの歌詞も替え歌にするから、いまみんなで一生懸命考えてるんだよ」
気がつけば、カレンダーは3月。去年、桜咲く入学式で幼い新1年生の手をひいてくれた6年生たちが、卒業の日を迎えようとしている。しかし、創立100周年に近いわが校の講堂は驚くほどアンティークで小さいため、卒業生の父兄席や招待席を設けると全在校生を収容しきれない。そのため、正式な卒業式の前に、在校生だけで「6年生を送る会」を行うのだという。そこで、今年1年生が披露するのが『ありがとう、さようなら』の合唱。送る会を前に、双子は家でも曲を口ずさんでいる。その歌声を耳にするたび、卒業生の親でもないのに、きゅっと胸がしめつけられる私……。子どもが歌う<別れの歌>はせつない。が、なにより私自身、6年生とお別れするのが寂しくて仕方ないのである。
「本当にこの学校でいいのか?」「双子は同じクラスでうまくやっていけるのか?」……私にとって、不安だらけだった公立小学校。その新生活は、約一年前の入学式の日、学校の玄関で出迎えてくれた6年生のお兄さん・お姉さんに、わが子の手を預けたところから始まった。彼らに手をひかれ、にこやかに話す子どもを見て、「もしかしたら大丈夫かもしれない」と、ホッと胸をなでおろしもした。まだ幼稚園の匂いがするわが子に比べ、6年生がどれほど頼もしく見えたことか!
以来、1年生の教室でのお話し会や、ランチルームでの会食、率先して交流をはかってくれた6年生。全校遠足や、運動会、アートフェスティバルなどの学校行事でも、常にリーダーとしてひっぱってくれた6年生。このわずか26名の最上級生は、1年生の手本としてとても見事に役をこなしてくれたのだ。
それだけではない。特に親しいわけでもないのに、町で会えば、必ず声をかけてくれる。入学して間もないわが双子を放課後、公園に誘ってくれる。地元の博物館に連れていってくれる。こちらが何も言わなくとも、帰宅時間になれば時計の読めない1年生を自宅まで送り、雨の日も風の日も「遊びたい」とせがめば必ず答えてくれた。<いまどきの子どもはクールで無責任>なんの根拠もなくネガティブに思い込んでいたそれまでの私にとって、目からウロコの連続だったのだ。
そんな彼らのコミュニケーションが、どれほど私を<学校の不安>から救ってくれたことだろう? そして私に<小学生の価値>を教えてくれたことだろう? この一年、教職員の指導はもちろんだが、私にとっても子どもたちにとっても何より一番の<先生>は、彼ら6年生の存在だったのだ。
6年生ともなれば身体も大きく、ランドセルを背負ってなければ、小学生に見えない。なかには茶髪の子どももいる。でも、そんな見た目や一部の事件報道だけで、子どもを決めつけてしまう大人がいまの世の中、ゴマンといる。以前の私がそうであったように、実際にコミュニケーションしたこともないのに、歪んだ常識をいかにも<もっともらしく>カラーリングし、結果、それが、子どもを追い詰めることになっても責任を感じない。情報社会のなか、いまどきの子どもたちは、常にそんな大人たちの逆風にさらされている。中学生になれば、そして高校生になればなおさらだ。でも、そんなとき、私は彼らの両親や学校とは違う立場で、盾になれたらと思う。願わくば、わが子のみならず、クラスの、学校の、町の、国のひとりひとりの子どもを見つめる大人でいたい。あの入学式の日、わが子の手をしっかり握ってくれた上級生へのせめてもの恩返しに……。公立小学校という地域と連携したコミュニティの一員として、できること。私も少しは自覚が出てきたのだろうか。
<ありがとう、さようなら6年生>。4月からは新しい生活が始まる。君に幸あれ!
(イラスト:Yoko Tanaka)
※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。
「おすすめ特集記事」の最新記事














 算数の教え上手
算数の教え上手 学校の危機管理
学校の危機管理 世界の教育事情
世界の教育事情 科学夜話
科学夜話



 この記事をクリップ
この記事をクリップ クリップした記事
クリップした記事
