
篠原 真子 PISAを語る。
PISAが描く世界と日本の教育の強み、弱み、そして未来
経済協力開発機構(OECD)による「生徒の学習到達度調査(PISA)」は、義務教育終了段階である15歳の生徒を対象にした国際的な調査で、これまでに5回、今この時点で6回目が行われています。日本では、成績が振るわなかった2003年の"PISAショック"や、2009年、2012年調査で得点が上昇した"V字回復"などが話題となりました。が、そもそもPISAとは何か? 目的は? その意義は? PISAが始まる前の計画段階から関わり、今もPISAの研究に取り組んでいる篠原真子・国立教育政策研究所総括研究官に、これまでの調査結果からわかってきたことも含め伺いました。
PISAの誕生

学びの場.comPISAの概要についてお話しいただけますか。
篠原 真子PISA(Programme for International Student Assessment)は、1980年代後半から経済協力開発機構(OECD)が世界各国の教育制度や教育政策について、共通の枠組みの中で比較するための指標(インディケータ)を開発するために取り組んできた教育インディケータ事業(INES Project:Indicators of Educational Systems)の一環として誕生したものです。
2000年調査から始まり、その後3年おきに2003年、2006年、2009年、2012年と、これまで5回実施され、その分析結果が公表されています。
調査内容は、「数学的リテラシー」「読解力」「科学的リテラシー」の3分野ですが、毎回3分野のうちの1分野について、他の分野よりも多くの調査時間を使って重点的に調べています。直近の2012年は、「数学的リテラシー」が中心分野でした。
2015年調査では、「協働問題解決能力」が新たに加わり、2018年調査では、「グローバル・コンピテンシー」を扱うことが予定されています。
調査対象は15歳の生徒で、日本では高校1年生が該当します。2012年調査では、世界65か国・地域が参加し、約51万人の生徒がこの調査に取り組んでみました。

学びの場.comそもそもどういった目的で始められたのでしょうか。
篠原 真子経済協力開発機構(OECD)による国際比較調査として始まりました。多くの先進諸国にとって、義務教育の成果について、エビデンス(数値・根拠)に基づく教育政策を立案・実施する重要性が認識されてきたこと、また、教育財政の「費用対効果」などを知るための指標が求められたということが背景としてあります。
日本でも、PISAの取り組みを通して、そこから得られた様々な知見が、文部科学省の各種施策や、中教審の議論に活かされると共に、全国学力・学習状況調査(全国学力テスト)の実施のきっかけともなりました。
学びの場.comPISAで見ようとしている力(リテラシー:活用能力)は、どういったものなのでしょうか。
篠原 真子PISAで見ようとしている力は、学校やそれ以外の家庭や地域で学んだり経験したりすることも含め、実生活で必要とされる知識・技能です。そのため「リテラシー」という言葉が用いられています。
調査対象が、多くの国や地域でこれから社会に出ていく手前の15歳に設定されていることからもわかる通り、市民社会での生活や個人の在り方が意識された問題となっています。
その中には、想定していなかった事態に直面したときに、目の前の課題を解決する道筋や方法を自分で切り拓いていく力も含まれます。つまり、持っている知識をいかに活用できるかがポイントになります。
正答は一つとは限らない
学びの場.comリテラシーを測定するために出題される問題も独特な形式です。テストというと、つい私達は教科・科目の知識の定着度を測るものを想定してしまいますが、PISAの問題はそうではありませんね。
篠原 真子実際の問題例を見てみましょう。(【資料1】)
これは、落書きに対する評価に関しての問題で、一人は落書きが反社会的な行為であるとし、もう一人は、これは芸術的な行為と同等で、コミュニケーションの手段であると主張しています。
この問題は、どちらの意見に賛成してもよく、正解は一つではないということで注目を集めました。それぞれの手紙の内容に触れながら、自分なりの言葉で説得力を持って、かつ根拠を示しながら説明できているかどうかが、採点の基準となっています。それが「論理的な力である」と言われたことが、結果公表時、新鮮な驚きを持って受け止められました。
もう一つ、見てみましょう。(【資料2】)
これはグラフをどう読み解くかという問題で、犯罪発生件数が棒グラフで示されており、1998年に508件程度、1999年に515件程度となっています。これを見て、TVレポーターが「激増している」と言った。それが適切かどうかを数学的に説明するという問題です。
この問題の正答は「適切ではない」というものです。例えば、「508件から515件への増加はそれほど多いとは言えない」というだけでは十分ではなく、その理由を説明しなくてはなりません。
犯罪という文脈から件数の増加がどのような意味を持つのか、また、件数全体から見て増加がどのような意味を持つのかを示す。あるいはまた、(グラフに示されていない)他の年度の変化についても検討しなければ、必ずしも激増とは言えないなど、経年変化の観点から指摘する。こうした説得力のある説明ができて初めて正答となります。
当時、日本の義務教育段階では、現実の統計データを取り上げ、それを分析するような数学の授業はあまり行われておらず、データを解釈していく力がこれからの社会では重要になると言われ、「こういう問題があるのか」「こういったことが問われるのか」と日本の教育関係者に大きな衝撃を与えました。
今では、「ピザ型」問題としてあちこちで紹介され、こうしたタイプの問題への取り組みはある種、馴染みのあるものとなっていますが、2000年、2003年当時の日本では、あまり見たことがないタイプの問題で、インパクトをもって受け止められました。
PISAが語り始めた各国・地域の特徴や課題

学びの場.com国際調査ということで、諸外国の成果も知ることができるようになりました。特に、最初の2000年調査の際はフィンランドが注目を集め、日本からも現地視察、“フィンランド詣で”が盛んに行われました。
篠原 真子1回目のPISA2000年調査の結果が出た2001年12月は、フィンランドが大きな注目を集めました。フィンランドは福祉の国として知られてはいましたが、教育においてそれほど高いパフォーマンスを示すとは一般的には思われていませんでした。それで詳しく調査結果を分析してみると、教員の能力や社会的地位が高いことや、かつて経済危機に陥ったことがあるけれども、教育に注目し、人材育成に積極的に取り組んだことで、経済・社会に活気をもたらしていることなどがわかってきました。
一方で、フィンランドの事例が「光」とすれば、「影」の事例としてドイツが挙げられます。ドイツでは、2000年調査の3分野すべてでOECDの平均点を下回り、その惨憺たる結果がドイツ国内で「PISAショック」と呼ばれました。
ドイツはその後、全日制学校を導入して授業時間を増加したり、州ごとにばらばらであった教育内容も、全国共通の教育スタンダードを策定するなど改善へと舵を切り、低かったパフォーマンスをばねにして、これまで以上に教育に取り組んできました。また、ドイツは移民を受け入れている国ですが、移民の背景を持つ生徒の成績が低位にあることがデータの分析によって明確に判明したので、そこに力を入れて成績を上げてきました。
PISAは、定期的な調査で経年変化の結果を見ていくことが、調査の最初の設計時から織り込まれていたので、2回目の調査以降は、自国の過去と現在の変化が捉えられるようになりました。また、これまでに5回の経験があるので、長いスパンの変化が明確になってきました。もちろん、国際比較調査ですから、他国との比較において、自国がどの辺りにいるのか、その自国の立ち位置も見えてきたと思います。

学びの場.comアジアや欧米諸国といった地域的な傾向や特徴なども出てきたということですね。
篠原 真子2009年調査に上海が初めて参加したときに、中国の1都市ではあるけれども、目を見張るパフォーマンスを示したことに欧米諸国は驚きました。
また、東アジアは総じて成績上位を占めています。日本も安定して成績が改善してきていますし、韓国、香港、シンガポールなども世界から注目を集めています。その一方、東南アジア諸国は平均得点では下位にあり、アジア全体を見ると二極化しています。
北欧諸国はパフォーマンスが高いのですが、実は近年、じわじわと得点が低下してきており、その原因究明が分析の対象となっています。
カナダ、オーストラリア、ニュージーランドは、移民が国のパフォーマンスを引っ張っている面白い国で、移民のおかげで高い成果を出している点が特色です。
英国や米国のパフォーマンスはOECD平均辺りですが、国際的には大きな影響力を持つ大国ですので、さらなる分析が求められています。
この10年余りの間に、それぞれの国や地域が、自国の教育とどのように向き合ってきたのか。それをデータが語り始めたということだと思います。
日本の「高いパフォーマンス」は教師が支える

学びの場.com「世界の中での日本」を見るとき、どのような示唆がありますか。
篠原 真子先ほど、ドイツの事例を挙げましたが、実は2003年調査では日本が「PISAショック」となりました。
ただ、その後、2003年から2012年の間に日本は着実に成績を上げてきており、その間の変化において、得点を上位から下位に四つの層に分けて見ると、成績下位層の得点の上昇が、日本全体の得点上昇につながったことがわかりました。成績下位層の底上げに必要なのは、きめ細かな指導です。もともと日本の先生方は、学習指導だけではなく生徒指導なども含めて、生徒の学校生活や家庭生活に総合的な目配りをして子ども達を育てています。その取り組みが、子ども達の学力形成に大きく効いたと考えられます。これは諸外国にはない日本の特性です。
具体的には、学校内で学習指導するだけで終わりとはせず、宿題も出し、生活習慣などの指導を行い、子ども達の学びに対する構えや、社会性の涵養も含め、課題によっては、クラスメートと協働して学びを進めるといったことも視野に入れた取り組みです。これは日本の教師がとても得意とすることです。日本は、諸外国と比べ研修が充実していますし、その中で研鑽を積み、非常に優秀な教師が育っているようです。今後も引き続き、優秀な人材を輩出するためには、これまで以上に、教師にインセンティブを与えることがポイントとなるでしょう。
日本のパフォーマンスの高さ、これがPISAにより改めてわかったことです。日本国内だけを見ていると、学校教育や教員に対して、人々はつい「厳しい視線」を送ってしまいがちですが、国際比較調査により人々の見方も変わるのではないでしょうか。教師の皆さんは、十分に高いパフォーマンスを示していることに、もっと自信を持っていいと思います。

学びの場.com一方で、調査結果を見ると、日本の子ども達の「自信のなさ」が気になります。
篠原 真子子ども達の自信のなさは、成績は良いのだけれど、数学に対する不安とか、将来、数学が仕事をするときに役に立つという気持ちが少ないという調査結果(2012年調査)に現れています。自信がなくても、成績が良ければそれでいいではないかという考え方もあるかもしれませんが、果してそうでしょうか。
そこで一つ示唆的なのは、フィンランドの傾向です。2000年当初もてはやされたフィンランドが2009年以降、成績が低下傾向にあります。その成績低下に先行して、興味・関心や読書などに楽しんで取り組んでいる生徒の割合が下がってきました。フィンランドで心配されているのは、こうした学習に対する態度の変化がじわじわと効いてきて、今後、取り戻せないほどの影響をもたらすのではないかということです。
その点で参考となるのは、オランダの事例かもしれません。オランダの生徒は不安感が少なく、国連児童基金(UNICEF)が2007年に公表した報告書でも、先進国(21か国)の中で、「子どもが幸せに暮らす国」第1位となりました。子どもが伸び伸びと学び、PISAでも安定的に良い成績を取っています。
オランダは歴史もあり、世界金融の中心ですし、欧州においても確固たる地位を占めています。サッカー・ワールドカップでも良い成績をとっている(笑)。つまり国際的なプレゼンスを示している国の一つです。
確かに、オランダへ視察に行かれた先生方のお話では、校内の規律が必ずしも良好とは言えないといった側面もあるようですし、オランダのような個人主義の国では、船に乗るのも自分次第、降りても落ちても自己責任という側面はあります。日本のように皆をしっかり船に乗せて進んで行く方が、社会的なコストを考えたときには良いのかもしれません。しかし、往々にして私達は、きゅっと縮こまって勉強しがちですが、伸び伸びとした雰囲気の中で勉強して同じパフォーマンスを示すのであれば、子ども達が自信を持ち、幸せを感じる方法をもっと取り入れるべきではないかと思います。
ランキングからマップへ
学びの場.com今後のPISAの展望についてお聞かせください。
篠原 真子調査開始当時、「目に見えない能力を測る」PISAに対して、日本ではその狙いをうまく受け止められない部分もあったかと思います。
しかしこれまでの蓄積によって、自国と他国の比較、それから自国の過去と現在とを比較することで、データから自国の教育の姿を理解し、見直し、これからの在り方を考える手掛かりが増えてきました。
PISAは、国際的な「学力ランキング」(【資料3】)の側面に注目されがちですが、得点と学習への態度との関係を見てみると「学力マップ」(【資料4】)として、諸外国の様子が一目でわかるものが出来ますし、また学力に人口を加味すると、人的資源の規模とも言うべき「学力スキル量」(【資料5】)が見えてきます。こうしたマップは、国や世界の学力の未来に対する色々なイマジネーションを与えてくれます。
確かにランキングや平均点は、わかりやすさという点では良い指標と言えるかもしれませんので、そこが注目されるのは当然かと思います。一方で、ランキングや平均得点では見えてこないものも多い。データをどう解釈するか、どう見ていくかというのは分析する側の視点によります。私達研究者も様々な観点で分析を行っていますが、データは公表されていますので、関心のある方は、自分なりの視点を設定して、統計ソフトを駆使して分析することができます。自国の教育の在り方を客観的に捉えるために、今後もますます多面的で多様な分析が必要だと思います。
確かにランキングや平均点は、わかりやすさという点では良い指標と言えるかもしれませんので、そこが注目されるのは当然かと思います。一方で、ランキング や平均得点では見えてこないものも多い。データをどう解釈するか、どう見ていくかというのは分析する側の視点によります。私達研究者も様々な観点で分析を 行っていますが、データは公表されていますので、関心のある方は、自分なりの視点を設定して、統計ソフトを駆使して分析することができます。自国の教育の 在り方を客観的に捉えるために、今後もますます多面的で多様な分析が必要だと思います。
時代は動いています。世界の動きに合わせてPISAそのものも変わってきており、2015年調査や2018年調査ではコンピュータを用いた調査になり、また、一人で解答するのではなく、多人数でコミュニケーションを取りながら、複雑で見慣れない課題や決まりきったやり方では解けないような課題に取り組んでいくことなどが検討されています。
OECDが最近強調しているのが、「教育の質は教師の質を超えられない(The quality of education will never exceed the quality of teachers)」というものです。日本の子ども達が、引き続き、良い成果を出していくためにも、ぜひ、日本の教師の皆さんには自信を持って日々の実践に取り組んでいただきたいと思っています。

篠原 真子(しのはら まさこ)
国立教育政策研究所研究企画開発部総括研究官
1963年生まれ。筑波大学博士課程、同助手、旧文部省を経て、2001年より同研究所。2014年より現職/文部科学省情報教育調査官。1995年のOECD-INES総会からPISAに関わり、2013年12月まで調査実施、分析などを担当。「連載:PISAが描く世界の学力マップ 第1~24回」(時事通信社『内外教育』、2014年)、国立教育政策研究所編『生きるための知識と技能5:PISA2012年調査国際結果報告書』(2013)、OECD編『PISAの問題できるかな?』(2010)、『PISA2009年調査 評価の枠組み』(2010)、『PISAから見る、できる国・頑張る国2』(2012)などPISAに関連した著訳書多数。OECD編『メタ認知の教育学~生きる力を育む創造的数学力』(共訳)を2015年8月に明石書店から刊行予定。
インタビュー・文:坂本建一郎/写真:言美 歩
※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。
ご意見・ご要望、お待ちしています!
この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)
「教育トレンド」の最新記事














 教育ウォッチ
教育ウォッチ 新刊紹介
新刊紹介 教材紹介
教材紹介



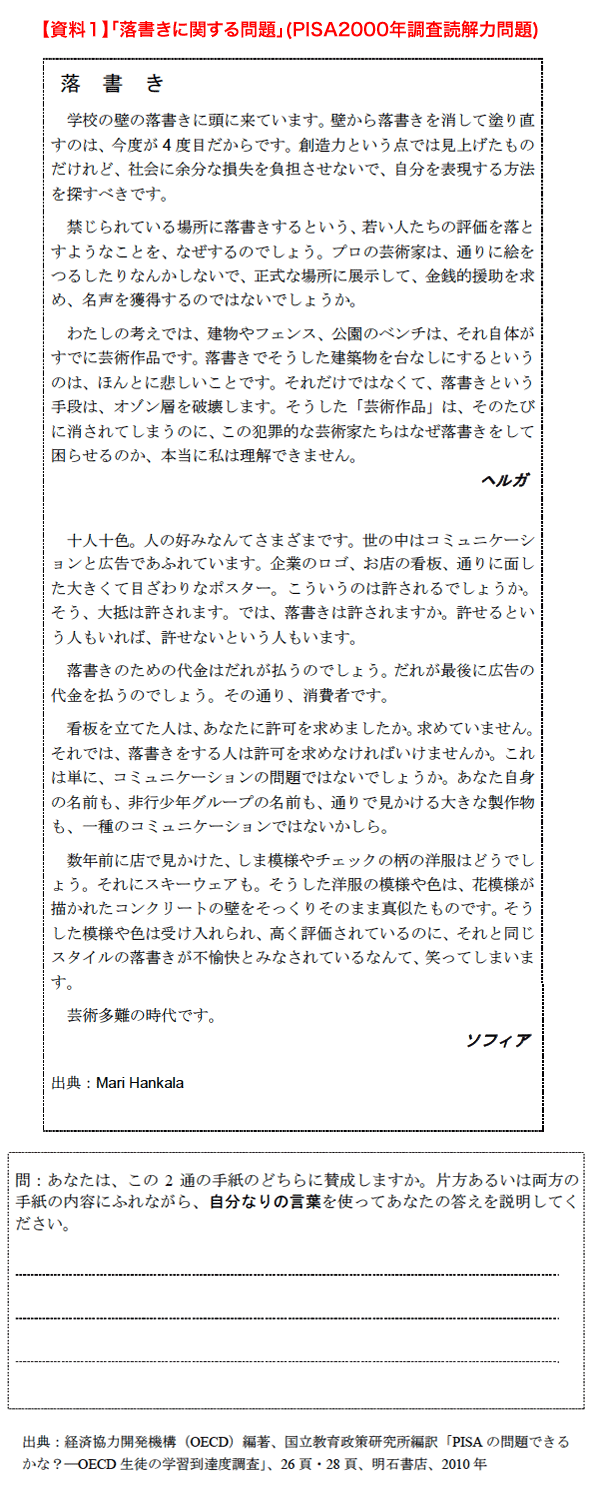
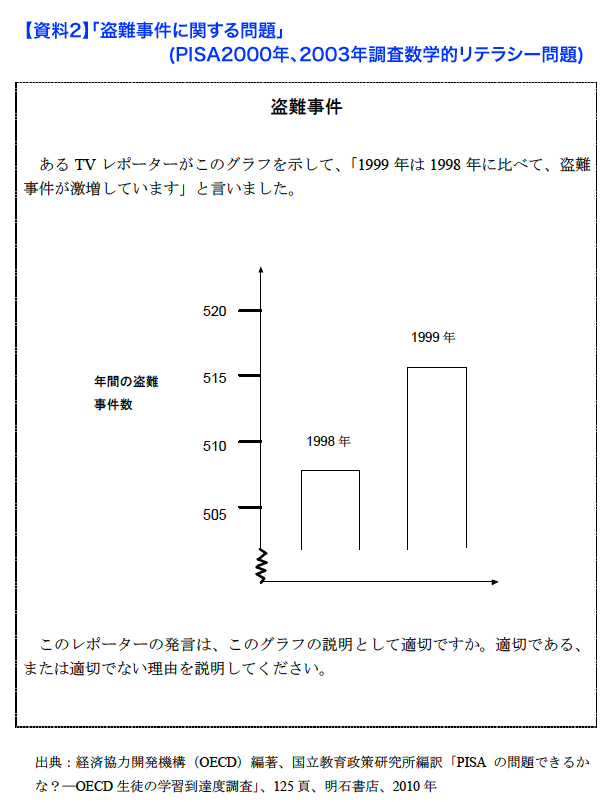
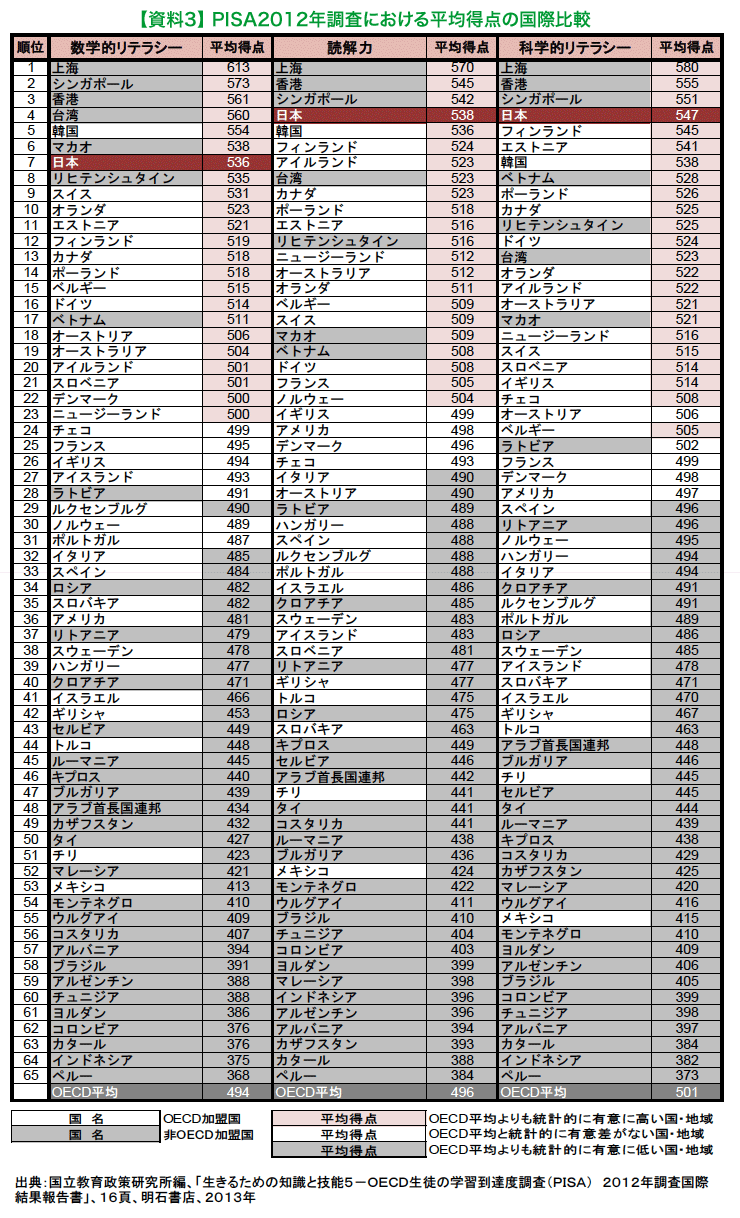
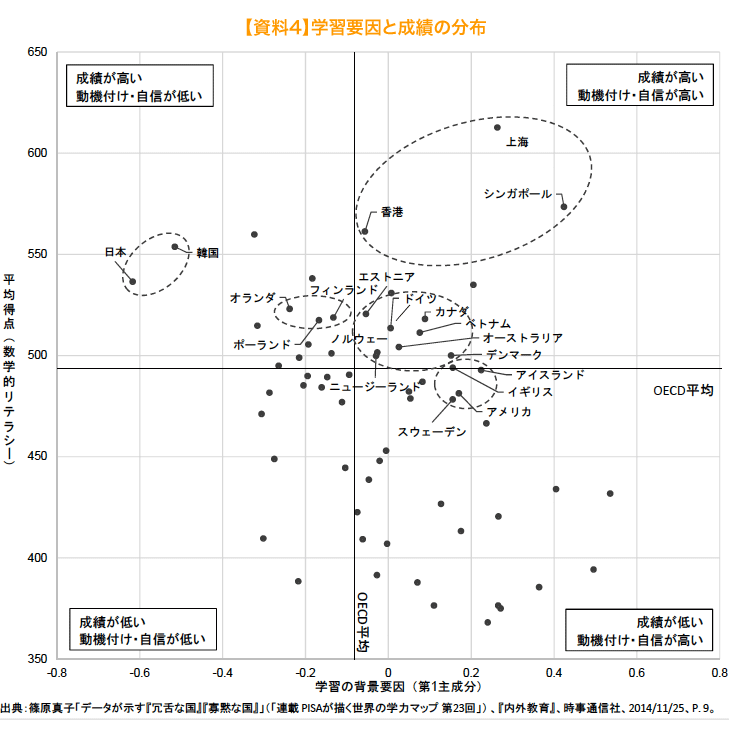
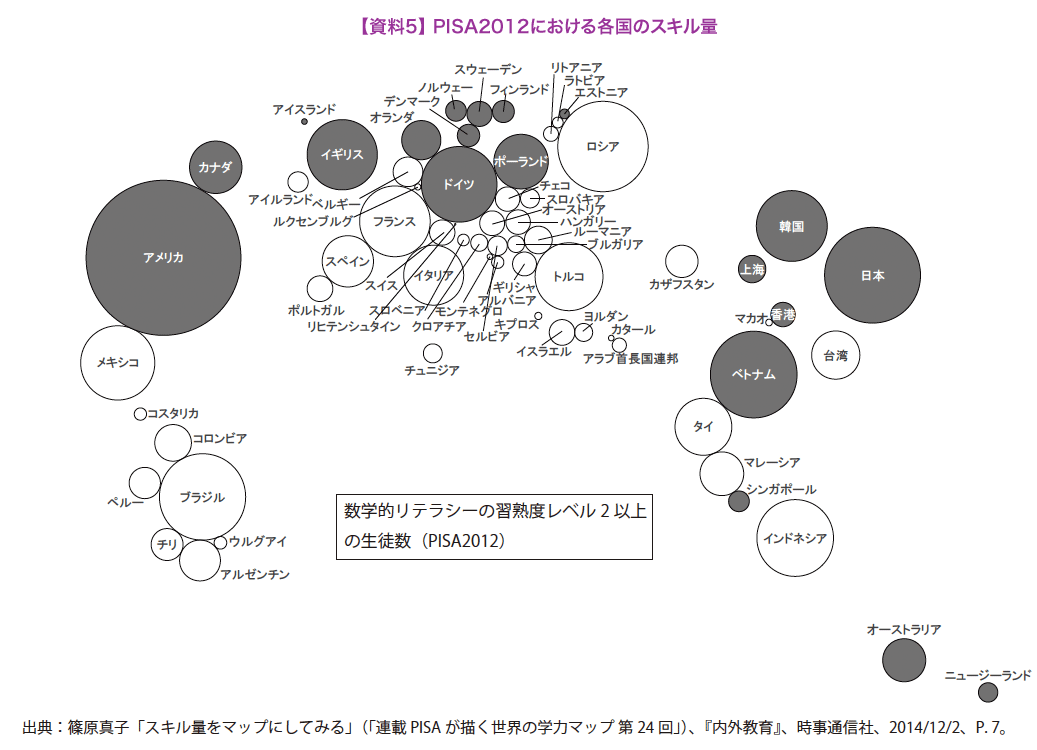
 この記事をクリップ
この記事をクリップ クリップした記事
クリップした記事 ご意見・ご要望
ご意見・ご要望
