
浜田博文 新刊『学校を変える新しい力』を語る。
教師のエンパワーメントとスクールリーダーシップの在り方とは?
浜田博文氏は学校経営研究の第一人者。このほど、学校管理職、ミドルリーダー、現場の教師それぞれに向けて、教職員の協働による学校改善のためのスクールリーダーシップ構築のノウハウをわかりやすく解説した書『学校を変える新しい力』を上梓した。「学校が、『組織』として活気に満ちていれば、教師の力も上がる」という浜田氏に、いま、学校に何が必要かを伺った。
「学級崩壊」は、先生個人の問題ではなかった

学びの場.com本日は『学校を変える新しい力』をめぐってお話をいただければと思います。
浜田博文今回の本は、さまざまな立場の学校の先生に読んでいただきたいと考えながら作りました。私自身は若い頃から、教育経営学という学問領域の中で、私の師に当たる錚々たる研究者の方々や先輩が編集した本に書かせていただく機会がありました。でも、そういう本の多くは、管理職の先生方を想定読者としたものか、もしくは研究者向けの本ばかりでした。
この10年くらいの間、「学校という場」を「組織」や「経営」という観点から捉える考え方を、管理職以外の多くの先生方に持っていただく必要があると、痛切に感じることが多くありました。それで、これまで取り組んできた研究を見直しながら、必ずしも管理職ではない、ごく普通の先生方に向けて本を作りたいと思ったのです。

学びの場.com「痛切」とおっしゃいましたが、具体的にはどのようなきっかけがあったのでしょう。
浜田博文1998年ごろだったと思いますが、「学級崩壊」が社会的に話題となり始めました。当時の国立教育研究所(現 国立教育政策研究所、以下国研)が当時の文部省(現 文部科学省)から委託を受けて、当時、国研にいらっしゃった小松郁夫先生(現 玉川大学教授)がチーフとなって調査を行いました。私もそのチームに入り、さまざまな学校に行って、聞き取り調査等を行いました。
そのころ、学級崩壊について書かれた本や、雑誌などで紹介されている記事は、担任の先生とクラスの子どもたち、そして保護者に取材をしてまとめられているものが多かったのですが、そうしたものの多くは、「学級崩壊」という現象を学級の中だけで起きている、いわば“閉じられたもの”として見ていました。

しかし、調査を行う中で分かってきたことは、「学級崩壊」を起こしている要因は、学級の内側だけではなく外側にもたくさんあり、例えば、同僚の先生方との人間関係やコミュニケーションの在り方、また、保護者や地域の方々との信頼関係等も、学級崩壊の原因として考えられうるということでした。さらには、地域の住民同士の協働性の在り方等も学級崩壊に関係することがあります。
ところが、当時の議論は、学級崩壊は「先生個人の指導力が足りない」から起きるという図式で語られがちでした。もちろん先生個人の指導力は、学級崩壊に関わる要素の一つではありますが、学級崩壊が回復していった例を見ると、教職員同士の関係が良好であれば、比較的スムーズに学級が持ち直していきますが、そうでない場合は、深刻化する一方であることが多いということも分かりました。

その後の学校教育の制度的な潮流として、指導力不足の先生を学校からいったん離すとか、教員評価を厳格化するという流れがありますが、先生個人の力だけでは解決できない事柄が仮にあったとして、それが個人の責任として負わされるとすれば、これは先生方のためにはならないし、ひいては子どもたちのためにもならない。そういうことを考えるようになりました。
先生方一人ひとりの実践も、学校の教職員の協働の中に位置付くということを何とか伝えられないだろうかと考えて、本書のメッセージとして込めました。
いま必要な、二つの「概念」

学びの場.com学校の力を高めることが先生たちの力をよりよく発揮させることにつながる。そのキー概念として、エンパワーメント(自己効力感の向上)と、スクールリーダーシップ(学校のことを考えて行動する志向性)という考え方が本書では示されています。これについて説明していただけますか。
浜田博文まず、「エンパワーメント」ですが、仕事に取り組むときに、あらかじめ決められたことをただやらされるよりは、一定の裁量を持って任されると「やる気」が高まるものです。そこには責任感も生まれます。
学校における先生方の仕事は、特にそういう性質を持っています。その理由はさまざまありますが、多くの先生は、日々、子どもたちと接していて、子どもが何らかの成長や変化を示すことに喜びを感じたり、やりがいを感じたりしていると思います。
そうした喜びを一番感じられる場面は、授業です。日々の授業やクラス運営を、自らの発想と努力で作り上げていく、そういう創造性のある行為が、やりがいや喜びにつながると思います。こうした環境のもとでこそ、一人ひとりの先生の意欲は高まる。それがエンパワーメントです。先生方の仕事に創造性や想像力は欠かせません。そうした力を発揮できる環境にある学校が、よい学校だと思うのです。
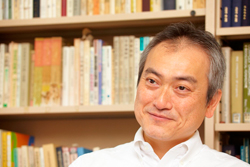
子どもたちが達成感を味わうことができて、先生方自身にも達成感がある学校には、保護者や地域の人も信頼を寄せてくれるでしょうし、その決め手は、先生方の自由度を自律性に基づいて発揮できる、新しいことにも積極的に取り組んで実現できるといった状態だと思います。
一人ひとりの先生が、何かに取り組めば、目の前の子どもたちが変わり、学年が変わり、学校が変わることを感じられることが大切です。新しいことを始めようとすると、つぶされてしまったり、あるいは自分の考えを表明しづらかったり、そういうことがあるとすれば、先生方のエンパワーメントを阻害するでしょう。どの立場の先生でもアイデアを出し合って、よいものはよいと認め合うことができれば、そのような一人ひとりの先生の実践が引き金になって学校は変わっていくことができる。それが「スクールリーダーシップ」という言葉の意味です。
「スクールリーダーシップ」とは、必ずしも校長のリーダーシップのことだけではなく、学校を構成するどのメンバーでも、学校を変えていくためのリーダーシップを発揮できるという意味です。

学びの場.com先生同士が「認め合う」「新しいことに積極的に取り組む」、こうした環境が先生方の潜在的な力を引き出していくのですね。
浜田博文今回の書籍の「あとがき」で、ある民間出身校長の述懐を引用しました。学校の先生方はコミュニケーションが足りないのではないか、という内容なのですが、その感触は私自身も持っていたものです。そもそも学校の先生の仕事は「個業性」が高いという性質があります。ホームルームや授業の進め方や、思考スタイルの特徴として、誰かと相談をしなくても、自分で決めてしまえば何でもできてしまうということがあります。そういうことから、コミュニケーションがなくても済んでしまうということがあるかもしれません。
また、「スクールリーダーシップ」との関連でいえば、どの学校にも、「学校教育目標」がありますが、自分の学校の学校教育目標について質問された際に、すぐに答えられる先生はなかなかいないと思います。なぜなら、「学校教育目標」は、自分の日々の授業などと関係があるとは思われていないからです。
授業については、教科の目標があり教科書もある。ですから、日々の授業はそれなりにこなしていけますし、それで成立するので、悪いとは必ずしも言いきれない。しかも、「学校教育目標」は、自分が赴任する学校に、はるか以前に設定されたもので、どのような議論があって、どのような経緯があって決められたものかも分からない。異動すれば、その「学校教育目標」とも離れてしまう。こうしたことから、学校の在り方と自分の実践がつながらなくなってしまいます。
そして、先生方の職務自体が、極めてあわただしいものとなっています。「多忙感」という言葉が使われるようになって久しいのですが、この言葉に「感」が付いているのは、ただ忙しいだけではなくて、仕事が断片的であったり、突然、予定もしていないような突発的なことが起きたりすることで生まれてくる感情があるからです。夕方に振り返ってみると、「今日1日何をしたのだろう」と、思い出せないようなことが続いてしまう。そういうところでは、かなり自覚的にコミュニケーションを取ることを考えないと、日常に流され、先生同士で意見交換をするような意識もなくなってしまいます。
こうしたことを考え合わせると、必要なコミュニケーションの場を設定してあげないと、特に若い先生などは孤立してしまうのではないかと感じます。
信念を持って、継続する取り組みを

学びの場.comでは、先生方は何から取り組めばよいのでしょうか。
浜田博文「学校を変える」というと、管理職にはできても、自分には無理だと考えがちです。確かに立場は重要で、管理職が変えようと思えば、改革の力が働きますが、そうではない場合は、どこから始めればよいか分からないということになるかと思います。
今回の本では、四つの事例を挙げています。「学校運営協議会」「研修の活性化」「中堅の高等学校の改革」「地域の合同運動会」です。この中で、中堅の高等学校の改革を例に挙げますと、この事例が含意しているのは、実は「校長のリーダーシップがあっても、それだけでは、学校は変わらないかもしれない」ということです。
私が校長先生方に向けた研修で講演をすると、質疑応答や懇親会などで、「学校を変えたいのだが、どう言っても変わらない先生がいて、結局、学校が変わらない」と話される方がおられます。しかし、日本の公立学校は、平等な人事配置がなされているのがそもそもの特徴。多様な先生がいるものです。その中には、テコでも動かない先生もいるでしょう。
テコでも動かない先生だけに注目していると、前には進めません。マーケティングの理論で、積極的に変わろうとする人がだいたい17%、その人たちが動けばそれに乗ろうとする人が33%、先行する33%が乗ればその後からついて行く人が33%。そして、絶対に動かない人が17%いるというものがあります(米国の社会学者、エベレット・M・ロジャース教授が提唱した「イノベーター理論」)。これを踏まえて考えると、最初から「テコでも動かない人」に目を向けてはダメです。逆に、積極的に変えようとする人(17%)と、そのフォロワー(33%)、つまり全体の50%の人さえ動けば、組織の全体が変わっていくというわけです。
学校は、変わる可能性をいつも持っています。毎年、人事異動がありますし、子どもや保護者も変わっていきますから。権限があろうとなかろうと、先生方はみな、教育実践を作り出す裁量は持っているわけですから、そこから始められればよいでしょう。
自分が「こう在りたい」と願う実践を何かしら持っているのであれば、職場の中で、同じような思いを持っている先生を見つけて、そういう先生同士の間で、とにかく実践を継続する。それがよいものであれば、子どもは絶対に評価してくれます。子どもが評価すれば、保護者も評価します。そこから生まれてくるものは、着実な評価の積み上げにもつながります。ですから、ぜひ自分の信念を持って、よい実践に取り組んでもらいたいと思います。
参考資料

浜田 博文(はまだ ひろふみ)
1961年山口県生まれ。筑波大学教授。博士(教育学)。専攻分野は「学校経営学」。筑波大学第二学群人間学類卒業後、同大学院博士課程教育学研究科単位取得退学。鳴門教育大学、東京学芸大学を経て現職。この間、バリー大学(米国フロリダ州)、南カリフォルニア大学(米国カリフォルニア州)で在外研究に従事。著書に『「学校の自律性」と校長の新たな役割』(一藝社)、『学校教育論』(共著・放送大学教育振興会)など。
インタビュー・文:坂本建一郎/写真:赤石 仁
※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。
ご意見・ご要望、お待ちしています!
この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)
「教育トレンド」の最新記事














 教育ウォッチ
教育ウォッチ 新刊紹介
新刊紹介 教材紹介
教材紹介



 この記事をクリップ
この記事をクリップ クリップした記事
クリップした記事 ご意見・ご要望
ご意見・ご要望
