環境教育の実践事例 自然に触れる機会が多い時期に体系的な学習を
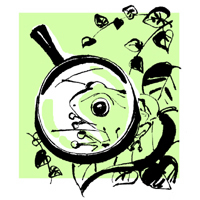
地球温暖化による気候変動、生態系の異変、砂漠化、水や食料の不足などが懸念され、学校教育の現場でも環境教育の重要性がますます増しています。 これからの時期は子どもたちが自然に触れる機会が多くなり、自然観察、ビオトープづくり、田んぼや里山の生き物調査、草花の栽培など、各地の小・中学校でさまざまな自然体験学習や環境教育の取り組みが行われます。今回は、小学校の環境教育の事例を取り上げ、その意義と課題、問題点を探りました。
増える学校でのビオトープづくり、自然体験学習
財団法人日本生態系協会が1999年度から隔年で行っている全国学校ビオトープ・コンクールでは、2005年度に計67校が受賞(文部科学大臣賞、環境大臣賞、国土交通大臣賞、学校ビオトープ優秀賞、奨励賞)しています。
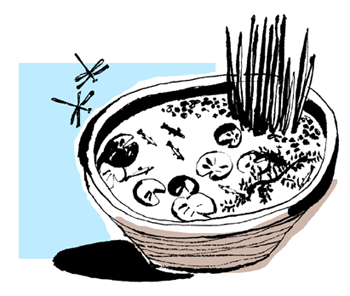
兵庫県教育委員会丹波教育事務所では、平成19年度(2007年度)から小学校3年生を対象に「環境体験事業」を始めようと準備を進めています。
この環境体験事業は、子どもたちが地域の自然に出かけて行き、地域の人々などの協力を得ながら自然観察や植物の栽培、動物の飼育など、五感(視覚、聴覚、触覚、嗅覚、味覚)を使って自然にふれあう体験型環境学習で、プログラム例として、(1)草花等を利用したクラフト作成、炭焼き、下草刈りなどの里山での体験、(2)苗作り、田植え、稲刈り、地元特産の野菜作りなどの田や畑での体験、(3)ホタルの飼育、希少植物の栽培、水辺の生き物の観察などの水辺での体験、(4)草花や昆虫の観察、ネイチャーゲームなどの地域の自然の中での体験などがあげられています。
平成19年度(2007年度)から3年間で段階的に実施校を増やし、平成21年度(2009年度)には兵庫県下の全ての小学校で実施する構想だそうです。
これら、自然体験学習のほかに、省エネルギー、生ゴミの堆肥化や紙の再利用などのリサイクルやリユースに取り組む学校も増えています。
表
環境教育に関する国際的な動向、小学校の環境教育の基本的な考え方や指導展開について解説した『環境教育指導資料 小学校編』(2007年3月 国立教育政策研究所教育課程研究センター発行)があげる環境教育に関する実践事例。
40年以上も続く緑化運動を軸に多様な環境教育を展開

埼玉県戸田市立美谷本小学校の花壇
埼玉県戸田市立美谷本小学校は、まだ環境問題や環境教育という言葉が知られていなかった1965年に埼玉県学校緑化コンクールで最優秀賞を受賞したことがあります。現在でも環境教育の一環として、教員と子どもたちが一体となってさまざまな草花や作物の栽培活動を行い、緑化運動を進めています。
年間を通して行われているのがサクラソウづくりです。サクラソウの栽培は苗づくりまでを栽培委員会の子どもたちが担当します。まず、土づくりからスタートし、校庭にある大きなケヤキなどの落葉樹の落ち葉を集めて木製の箱に入れ、それに糠を加えて発酵させて腐葉土をつくります(この腐葉土はカブトムシの生育にも使われます)。
春に、サクラソウの花から落ちた種が発芽したできた苗を一つ一つ育苗ポットに入れて育てます。そのまま夏を越して秋になってから、苗を鉢に移し替えて教室の中で冬を越します。この間、毎日水やりを欠かしません。冬休みが過ぎると栽培委員会から各クラスに鉢植えのサクラソウが受け渡され、クラスで育てられます。
クラスでは、毎朝ベランダの外に出して水や肥料を与え、下校時には教室の中に入れて霜を防ぎます。サクラソウは冬の日差しを浴びながらすくすくと育ち、花を咲かせて、卒業式や入学式の会場を飾ります。

埼玉県戸田市立美谷本小学校の腐葉土をつくる木箱
サクラソウ以外の全校での取り組みとして、さつまいもづくりがあります。学校に付属している畑を耕して苗を植え、草取りや水やりなどの世話をして秋に収穫します。
また、植樹をして樹木を育て、緑を増やす活動もしています。
小動物の学校飼育として4羽のウサギを飼っています。学校が休みになる土曜日、日曜日や夏休みなどの長期休暇には飼育委員会の子どもたちや教員が世話をしに来るなど、教員と子どもたちが一緒になって育てています。
総合学習の生活科の授業では小麦をつくり、実った小麦を石臼でひく体験活動や花を摘んで押し花づくりも行いました。
また、学校の近くにある自然豊かな彩湖道満グリーンパークで、1~2年生は生活科の体験学習として草すべりや虫探し、どんぐり拾いなどを、3~6年生は総合的な学習の時間や理科の学習を行います。
地域と協力する活動として、同じ市内の市立美女木小学校とともに、国道298号線の道路美化活動を支援するボランティア・サポート・プログラム(VSP)の一員となり、6年生が「花ロード美女木」(2.12km)の美化運動(ゴミ拾いや清掃など)や花壇の花植えなどの活動を行っています。
美谷本小学校校長の鷲谷三義さんは、「サクラソウの栽培やウサギの飼育は、栽培委員会や飼育委員会のこどもたちが中心となって年間行事の中で、当番活動としてやっています。草花や動物を大事にする気持ちが、物を大事にする、環境を大事にする、他の人を大事にする心を育てることにつながっているように感じます。こうした心が育って、より深く環境問題を理解し、他人への思いやりが生まれ、それがケンカやいじめの減少につながってくれればよいと思います。草花や樹木、動物などをもっと知ろうとする探求心が育てば、他の教科の向上にも大いに役立つと思います」と指摘しています。
学校版ISOプログラムを推進。ビオトープ、壁面緑化、リサイクルなど総合的な取り組み

東京都目黒区立向原小学校のビオトープ
東京都目黒区立向原小学校は、古い商店街と住宅地に囲まれた地域にあり、家屋が密集していて東京都内でも最も樹木が少ないところといわれていますが、近くに立会川緑道があり緑化運動が盛んです。同校では、13年間にわたって環境への取り組みを行ってきました。休み時間に水道水の出しっぱなしに気を付けたり、トイレなどの電気を自主的に消したり、掲示板にその日の環境について気がついたことを書き込む子どもの姿が見られるなど、子どもたちの生活の中にも環境への配慮が定着しています。
特色ある教育活動として環境学習の推進が掲げられており、父兄や地域の人たちからも環境教育を継続して進めてほしいとの要望が多いそうです。
学内では子どもたちがつくる環境委員会などが中心となって各学級に呼びかけて行う牛乳パックやアルミ缶、古紙の回収などの取り組みを行っています。
また、自然体験学習では、1999年に全児童が参加してビオトープづくりを行い、その模様を2001年8月に開催された子ども国連環境会議全国大会で研究発表しています(テーマ「つくろう生き物たちと共生できるまち」)。
平成18年度(2006年度)からは、目黒区が推進する学校版ISOの試行校として、いち早く学校版ISOプログラムの実践に取り組んでいます。
(1)電気や水のむだ使いをなくし、エネルギー・資源を大切にします、(2)エコスクールとして地域に根ざした環境学習を進めます、と宣言し、環境学習活動として生活科や総合的な学習の時間の中で、「プールでヤゴ救出作戦」(1年生)、「ミミズを育てよう」(2年生)、「生ゴミ堆肥づくり」(3年生)、「ビオトープの観察と保全」(4年生)、「学校周辺の緑化推進」(5年生 公園や緑道等の花壇を手入れするボランティア団体グリーンクラブへ参加し、遊歩道の花壇に草花の苗を植え、季節ごとに植え替えをして植物と親しみ、ふれあう機会を増やす)、「向原農園(学校農園)で有機野菜を育てる」(6年生)などに取り組み、今年度からは体育館の壁面緑化の取り組みも始めました。
また、省エネルギー・省資源活動として、「水道の水を出しっぱなしにしない」「バケツに水を入れてぞうきんを洗おう」「使わないときはこまめに電気を消そう」などの活動に全校で取り組んでいます。

東京都目黒区立向原小学校の学校農園
また、学力重視に大きく傾きつつある学校教育の中での環境学習について、「知識の詰め込みだけで、想像力や表現力がともなわなくては真の学力とは言えません。やはり心の学習も必要です。心が育つから真の学力が伸びていくのです。心の育成の面に大きな力がある環境学習は、子どもたちが真の学力を身につけるために大いに役立つと思います」と言います。
小松さんは、向原小学校の教育の目標として「よく考える子」「じょうぶな子」「やさしい子」の3つにプラスして「かかわりを大切にする」を掲げ、「公教育の役割は人間づくりにある」と述べています。
小学校時代は知育よりも心を育てる時期です。この時期に自然とのかかわりを持つことで人との思いやりや豊かな想像力、表現力の基礎が生まれてきます。学力重視という言葉に引きずられて、いたずらに知識の詰め込みに走ると、こうした芽を摘み取ってしまう恐れがあります。
表
学力重視の中で、環境教育がおざなりにされている?
1990年代まで、環境教育は小・中学校、高等学校で児童・生徒の発達段階に応じて社会科、理科、地理、保健体育などの教科の中で行われてきましたが、1989年の学習指導要領の改訂によって、道徳や特別活動でも行うこととされました。そして文部省の『環境教育指導資料』(中学校・高等学校編1991年、小学校編1992年)が発行され、学校における環境教育の役割や新学習指導要領の中の環境教育にかかわる内容の解説が行われました。
2002年からは、国際理解、情報、環境、福祉、健康などの課題については、学校の実態に応じて総合的な学習の時間で扱うものされています。
2006年に制定された新教育基本法のもとで見直された『環境教育指導資料 小学校編』(2007年3月)では、「環境教育とは、『環境や環境問題に関心・知識を持ち、人間活動と環境とのかかわりについての総合的な理解と認識のうえに立って、環境の保全に配慮した望ましい働き掛けのできる技能や思考力、判断力を身に付け、持続可能な社会を目指してよりよい環境の創造活動に主体的に参加し、環境への責任ある行動がとれる態度を育成すること』と考えることができる」とされています。
小学校における環境教育のねらいについては、「環境に対する豊かな感受性の育成」「環境に関する見方や考え方の育成」「環境に働きかける実践力の育成」とあり、環境教育で重視する能力と態度の例として、「課題を発見する能力」「計画をたてる力」「推論する力」「情報を活用する力」「合意を形成しようとする力」「公正に判断しようとする力」「主体的に参加し、自ら実践しようとする態度」があげられています。
こうした学校での環境教育に対して、「学力重視の中で環境教育がおざなりにされている」「学力向上のため、主要教科の指導で手一杯。評価、受験に関係のない環境教育に手が回らない」「学校や教員が何をしたらよいのか、よく分からない中で環境教育が進められている」「具体的な指導の進め方が見えない」などの声もあります。
また、「日本では環境教育はまだ歴史も浅く、必ずしも各教科や総合的な学習の時間で行われる内容がうまく連携しているとは言い難い」「体系的な環境教育の指導方法がない」などの声があります。
各教科の教員間の連携や環境教育を体系的に行うためには、学習をどのように展開するかなどが今後の大きな課題となっています。
知識と体験の積み重ねが自然環境への好奇心を生み、探求心へと育てる

武蔵野市立むさしの自然観察園に生息するチョウ
自然環境の保全や自然環境教育を行うNPO法人武蔵野自然塾は、東京都青梅市にある二俣尾・武蔵野市民の森における自然観察、ハイキングなどの企画や植生調査活動、武蔵野市立むさしの自然観察園(北町ビオトープ)の管理・運営や自然体験プログラムの企画、市および学校からの委託による小学校の環境教育特別授業、学校ビオトープの自然観察指導、ビオトープ自体のメンテナンス、こども自然体験指導者養成講座の開催などを主な活動としています。
理事長で環境カウンセラーの梅田彰さんは、「今、『気づき』という言葉と概念を重要視するあまり、自然環境教育の大切なことが忘れられています」と指摘します。
現場における自然観察や野外生活体験指導において、あえて教えることをせず、子どもたちに自分でやらせる、考えさせることを最重点において指導する方法がとられているというのです。
梅田さんは、「気づく、感じるということは、あくまでも記憶の中に残っている過去に得た知識や体験と比較して、気づき、感じるのであって、自然との触れ合いが断ち切られた生活をしている都市部の子どもたちには、自然に対する知識の蓄積が不足していますので、気づくにも気づきようがなく、感じたとしても、きれい、気持ちよい、大きいなどといった極めて初歩的な感情や印象でしか感じることができないのです。自然の仕組みの驚異に気づいたり、感じたりすることができないのです」と言います。

武蔵野市立むさしの自然観察園のビオトープ
自然環境を理解するには、まず身の回りの動植物や空気、水、土壌などについての基礎知識を知ることが大切で、その基礎知識の上に立ってさまざまなものを比較することで、「不思議だ!」「なぜだろう?」「そうだったのか!」と感じたり気づいたりし、自然環境を見る目が養われます。
しかし、現在の理科は受験体制の中で学力を重視した内容になっており、身の回りの動植物をたくさん覚えるのではなく、メンデルの法則やカエルの解剖などのような日常生活から離れた知識習得に重点が置かれています。
梅田さんは、「子どもたちが、できるだけ多くの動物や植物に接する機会をつくり、それを覚えさせてデータを蓄積させることが大事です。その際には名前だけでなく、そのものの見どころや区別のしどころなど、他との識別のポイントを教え、視る、聴く、触れる、匂いを嗅いでみる、味を確かめるなどの五感を使って印象を強めたり、面白い解説をして子どもたちに興味や好奇心を持たせる工夫が大切です」と言います。
子どもたちが多くのものを何度も見て、興味を持って名前を覚え、記憶データを増やす。これが「気づき」や「感じる」ための原点で、探求する心を育てる方法といえるでしょう。
他教科と関連しながら、最重要の必須教科として学習を
「知りたい」「調べたい」という子どもの好奇心を満たし、その意欲を持続させるためには優秀な指導者を養成すること、疑問や知りたいことをすぐに調べることができる図書資料を揃えること、関連ホームページにアクセスできる環境を整えること、子どもたちが本や図鑑をホームページで検索するなどコンピュータを扱うための技術指導も重要です。こうした環境整備が行われることで、子どもたちの探求心はさらに高まり、主体的に環境学習に取り組む姿勢が生まれてくるようになるでしょう。
そしてもう1点。現在、環境教育は特定の教科ではなく、各教科の関連する授業内容に応じて取り上げられたり、特別活動、総合的な学習の時間の中で行われていますが、地球環境問題は人間と人間、自然と人間のかかわりの環の中で起きる問題で、人間の未来を左右する最も重要な総合科学として研究されてきています。
小学校における環境教育も、総合学習として他教科と関連しながら、一つの重要な必須教科(特定教科)として、きちんと体系的に学習が行われる必要があるのではないでしょうか。
その他の環境教育参考資料
| 【学校版ISOプログラムについて】 学校版ISOプログラムとは、学校全体で環境活動に取り組む仕組みで、「環境学習の推進」「環境負荷の低減」「地域に根ざした環境活動の推進」を実践していくものです。 学校版ISOプログラムはPDCAサイクル(計画→実行→点検→見直し)に基づき、環境活動を実践します。その具体的な流れは、 |
|
| [計画]Plan | |
| (1)調べる | 環境について学んだことやエネルギーの使用量、ゴミの量などを調べます。 |
| (2)宣言する | 学校でどのような環境活動をしていくかを宣言書にまとめ、発表します。 |
| (3)計画を立る | いつ、誰が、何をするのか、具体的な計画を立てます。 |
| [実行]Do | |
| (4)実行する | 計画に基づいて環境活動を実践します。 |
| [点検]Check | |
| (5)点検する | 環境活動が目標通りにできているか、点検します。 |
| [見直し]Action | |
| (6)見直す | これまで実践してきたことを見直して、さらによくするにはどうしたらよいか、考えます。 |
そして、(1)にもどって、次の環境活動のために調べて、計画を立てて実行します。この繰り返しによって、毎年、環境活動のレベルアップをはかり、環境問題の解決(持続可能な社会の実現)に向けて進みます。
【省エネルギー・省資源活動(リサイクル、リユース)の例】
| ●節電 | 教室やトイレなどの電気をこまめに消す、冷暖房の温度を控えめに設定するなど。 |
| ●節水 | 水道の水を出しっぱなしにしない、雨水などを上手に利用するなど。 |
| ●ゴミの減量 | ゴミをきちんと分別する、使えるものは再利用する、生ゴミを堆肥化するなど。 |
| ●環境意識を高める | 省エネルギーやリサイクル、リユースのポスターをつくって貼る、校内に無駄がないかを点検(パトロール)するなど。 |
【環境学習活動の例】
|
・
|
自然観察をし、ネイチャーゲームを行う |
|
・
|
生ゴミを堆肥にする |
|
・
|
自然学習体験として農作業を行う |
|
・
|
空き缶やペットボトル、古紙の回収を行う |
|
・
|
学校の花壇や地域の公園、遊歩道の花壇に花を植える |
|
・
|
校庭や地域の公園などに緑を増やす樹木を植える |
|
・
|
ビオトープをつくり、生物が住めるようにする |
|
・
|
ミミズを増やして土づくりをする |
|
・
|
落ち葉を集めて腐葉土をつくり、花を植えたり、カブトムシを育てる |
|
・
|
地域や学校の環境を調べ、環境レポートや環境新聞をつくる |
|
・
|
地域の森林、川、緑地、生物が住むところを調査し、環境マップをつくる |
|
・
|
台所で捨てられる廃油で石けんをつくる |
|
・
|
大気汚染や酸性雨について調べる |
|
・
|
牛乳パックを使って紙をすき、ハガキをつくり友だちに送る |
|
・
|
地域の工場と環境問題の関係について調査する |
|
・
|
町の発展と自然環境の変化について調べる |
|
・
|
自分たちに、どんな環境活動ができるのか、みんなで調べてみる |
構成・文:矢崎栄司 イラスト:あべゆきえ
※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。
ご意見・ご要望、お待ちしています!
この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)
「教育トレンド」の最新記事














 教育インタビュー
教育インタビュー 新刊紹介
新刊紹介 教材紹介
教材紹介



 この記事をクリップ
この記事をクリップ クリップした記事
クリップした記事 ご意見・ご要望
ご意見・ご要望
