不登校のいま
不登校の児童・生徒の増加が止まりません。「登校刺激を与えずに待つ」という考え方の見直しが始まり、「関わりや働きかけ」が大切だとする答申も出されました。いま、不登校の子供たちに対しては、学校はもちろん、フリースクールなどでもさまざまな動きが出ています。今回は、そんな新しい動きを探ってみます。
■不登校13万人時代
(8月8日の文部科学省の学校基本調査速報では、不登校とされた小中学生は13万1千人で、前年度を5.4%を下回ったと発表されました。しかし、学校によってはフリースクールに通う子どもは出席扱いするケースもあり、この数字だけで問題が改善の方向に向かっていると考えるのは時期尚早と言えるでしょう。)
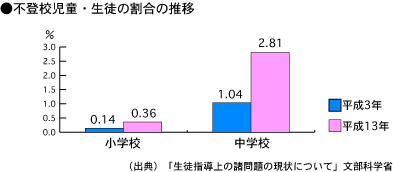
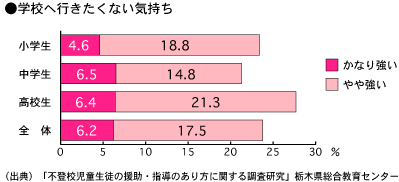
こうした状況を受け、文部科学省から発表された答申の中で、不登校への対応・防止のための5つのポイントがあげられています。
1)将来の社会的自立に向けた支援の視点
2)連携ネットワークによる支援
3)将来の社会的自立のための学校教育の意義・役割
4)働きかけることや関わりを持つことの重要性
5)保護者の役割と家庭への支援
実は平成4年にも、不登校の対応に関する答申が出されています。その中では、
・不登校は特別な子に起こる問題でなく、どの子にも起こりうる
・登校の促しが状況を悪化させることもある。場合によっては、学校の指導以外の他の適切な指導も検討する必要がある
という2点が、大きなポイントでした。
なぜなら、それまでは「子どもが学校に行かないのは親の責任」との考え方が主流でした。またなんとか子どもを学校に戻そうとする対応が中心でした。そのような中で、平成4年の答申は、不登校に対する見方を変え、子どもや親を精神的に救うきっかけになったのです。
今回の答申でも、登校の働きかけをするにあたっては
・その子の現状や不登校の要因・背景を把握する
・不登校の当事者の声に耳を傾ける
という2点を考慮することが大切だという内容がつけ加えられています。
■不登校をめぐるさまざまな活動
現在、小学校6年生になるある男の子は、2年生の2学期から不登校を続けています。その子のお母さんは次のように話しています。
「不登校を始めたのが2年生ですから、これが原因、とはっきり自分から話せる状態ではありませんでした。私も何がなんだかわからない、という時期が長く続きました。外に出ること自体を嫌がっていますので、子供を相談機関に連れて行くこともできない、フリースクールなどにも行かれません。学校の先生も気にして来てくれましたが、学年が変わるたびに、担任の先生も替わり、同じ学校なのに、こうも対応が違うのか、と驚くことも多いです」。
実際に、学校の支援体制は、学校ごと、そして究極的には担任ごとにまちまちのようです。
たとえば、学校関係者を対象としたある調査によると、
・ 子どもとの連絡は担任がしているが、養護教諭や学年の先生たちと常に相談を しながら、たくさんの先生たちに支援を受けている。 (小学校)
・ 教頭を中心に養護教諭・専科・担任で対応しており、担任の精神的な負担が軽くなった。(中学校)
・ 教育相談の先生が交換日記や話し込みをしてくれている。(中学校)
・ 前年度の担任と連携して取り組んでいる。(中学校)
などの取り組みが報告されています。
ただ、同じ取り組みをしていながら、不登校が改善された例もありますし、改善されていない例もあります。
一方、家庭の取り組みでは、
●改善された事例
・ 協力的で小さな変化も報告してもらう。生活が不規則にならないことに努力している。(小学校男子)
・ 無理に登校させようとしていたのが、担任との相談で長い目で見守るという態度 に変化していった。(小学校男子)
・ 初めのうちは苦情の電話が多かったが、最近は減ってきた。(小学校女子)
・ 両親とも協力的で、特に兄弟のアドバイスが励ましになっている。(中学校女子)
・ 本人が変わらねばと本人まかせだったが、3年になったら協力的になった。(中 学校男子)
●改善されなかった事例
・ 学校からの一方通行で終わっている。(小学校女子)
・ 保護者が感情的になり、責めたり、甘やかしたりで、落ちついて話ができない。(中学校女子)
・ 欠席が長期化しているため、保護者も「どうにかなるだろう」と消極的である。(中学校男子)
などが報告されています。同じ取り組みをしていても、やはり子供ごとに結果は変わってきています。
学校に戻る、ということではなく、フリースクールなどでの支援も活発です。フリースクールとは、国や行政が作る学校ではなく、国民が自由に作り、内容も、 国や行政のカリキュラムから離れて自由に教育活動を行っている教育機関のこと。
フリースクールのネットワークである「日本フリースクール協会」、特定非営利活動法人(NPO法人)の「楠の木学園」「東京シューレ」などさまざまな団体が全国各地で活動しています。
たとえば、「東京シューレ」では、6~20歳の子どもや若者が、東京都北区、大田区、新宿区にある3スペースに通ってきています。その数、あわせて約200人。通い方、過ごし方、学び方、プログラムは子ども自身が選択します。
最近では、インターネットでの情報交換も盛んで、「不登校を考えるネットワーク」「不登校の生徒、お父さんお母さんのためのページ」「不登校の子供をもつ親たちのホームページ」「「不登校・引きこもりのページ」「不登校からの旅路」など、家庭にいながら、悩みをぶつけたり、情報を得たりすることもできるようになってきています。
■自治体が不登校の児童・生徒の教育に乗り出す
このような中で、 埼玉県志木市の教育委員会は、不登校の小・中学生の自宅へ教師を派遣して個別授業を行う「ホームスタディー制度」を2002年度から導入しました。学校での心理的なプレッシャーから登校できない児童・生徒に平等に教育の機会を与えることが目的です。個別授業を受ければ出席扱いとなります。
ホームスクールとは、学校に行かずに家庭を学習の中心にする教育の在り方で、米国では約200万人がこの方法で教育を受けていると言われています。日本ではまだまだなじみが薄く、民間団体などの支援組織はありますが、自治体が制度化するのは全国で初めて。これまで事実上放置されてきたに等しい「不登校の児童・生徒の教育」という問題に、自治体として初めてメスを入れる志木市の試みといえます。
制度の実施は、まず臨床心理の専門家や教育関係者らでつくる審議会を設置することから始まります。不登校の小中学生とその家族がホームスクールを希望した場合、審議会で不登校になった原因や経緯を検討し、制度の対象とするかどうかを判定。対象に認定されると、家庭に元教員などの有償ボランティアを派遣し、学力を考慮しながら文科省のカリキュラムに沿って在宅学習を支援します。志木市は「基礎学力を身に付けて学校に復帰してもらうのが目的」とし、「ホームスクールはあくまで一時的な教育の場」との考え方です。
これに対して、日本ホームスクール支援協会理事長の成田滋・兵庫教育大教授は「公立小中学校の設置者である市が、教育はすべて学校で行うという考え方から一歩を踏み出した画期的な制度」と市の立場とは違った解釈で評価。一方、別のホームスクール関係者は「不登校の児童、生徒にとって唯一安らげる場所である家庭にまで学校復帰を目的に先生がやって来るなんてぞっとする。子供はさらに精神的に追い込まれることになるのではないか」と制度の実施に危惧の念を抱いています。
昨年度、同制度を申請したのは小学生12人、中学生7人の計19人でした。対象の児童・生徒19人の一人ひとりの原因・状況に、適応するプロジェクトチームがそれぞれ設置され、月1回の会議を開き対応しています。メンバーはその小中学生の学級担任、臨床心理の専門ケースワーカー、保護者に対応する専用相談員など、その児童・生徒にとって必要なスタッフから構成されます。
この制度を利用した志木市立第三小学校の山本邦男校長は、次のように語ってくれました。
「ホームスタディ制度がなかったら、一人の児童に学校だけではここまで対応できなかったと思います。学校と非常に密に連携する温かい制度ではないでしょうか。学校を休む、ということに行政が関わっているという批判もありましたが、実際に実施してみて、親と学校の判断がきちんとしていれば、学校に来ることを押しつけるあまり子どもの逃げ場を封じ込めてしまうような形で機能することはないと思います。また、学校に来るのを前提としている、という批判もあるようですが、子どもの個性を殺さないで、教師の努力で何とかなるという学校のあり方が、必ずあるはずだと私は信じています」。
志木市の試みはまだ始まったばかりですが、今後に大きく期待できそうです。
執筆:長橋由理 イラスト:Yoko Tanaka
※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。
ご意見・ご要望、お待ちしています!
この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)
「教育トレンド」の最新記事














 教育インタビュー
教育インタビュー 新刊紹介
新刊紹介 教材紹介
教材紹介



 この記事をクリップ
この記事をクリップ クリップした記事
クリップした記事 ご意見・ご要望
ご意見・ご要望
