教員人事権問題の本質とは何か 市町村への人事権移譲をめぐって
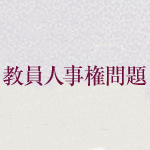
大阪府の橋下徹知事が、都道府県教育委員会が持っている公立小・中学校教員の人事権を市町村教育委員会に移譲できるようにすることを文部科学省の鈴木寛副大臣らに要望したことを受け、同省は4月末に市町村への人事権移譲は現行制度下でも可能であるとの見解をまとめた。早ければ2011年度にも教員人事権の移譲が大阪府などで実現することになりそうだが、これによって公立小・中学校の教育はどう変わるのだろうか。
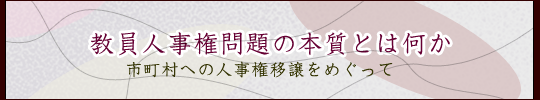
橋下知事の主導で2011年度から具体化へ
そもそも市町村立の小・中学校に勤務する教員の身分は、学校設置者である市町村の職員という建前になっている。ところが、教員の採用、人事異動、処分などに関する人事権は、都道府県と政令指定都市(以下、都道府県と略す)が持っている。市町村教育委員会は教員の人事異動などで都道府県教育委員会に内申することはできるが、直接に教員人事を行う権限はない。つまり、公立小・中学校の教員は、形式的には市町村職員であるが、実質的には都道府県職員として扱われているというわけだ。これは、教員給与を国と都道府県が負担するという「義務教育費国庫負担制度」とセットになったもので、給与の負担者(都道府県)が人事権を持つという原則に基づいている。これによって都道府県は、県内全体にわたる広域人事を行うことが可能になり、市町村や地域ごとに教員の質にばらつきが出ることを防いで、義務教育の質の均等化を図っている。
ところが、近年になって都道府県による広域人事への批判が高まってきた。その理由の一つ目は、国全体の地方分権化への流れだ。実際に教員が勤務しているのは市町村立学校であり、その人事権も市町村が持つべきだという主張が大規模自治体を中心として出されるようになってきた。そして、二つ目は特色ある学校づくりの推進、学校選択制の導入など市町村による独自の教育改革が進められるようになったことだ。都道府県の人事異動方針に基づいて転勤を繰り返すため、どうしても勤務地の市町村は「通過地点」という感覚が強くなる。いわゆる改革派の首長などの間では、このような教員の意識が独自の教育改革の妨げになっていると批判する意見が少なくない。市町村への教員人事権の移譲を可能にすることを求めた橋下知事の意向も、これらの事情を踏まえたものだ。
橋下知事の求めに対して文科省は、特別条例を大阪府が制定すれば、教員人事権の移譲は現行制度下でも可能という見解を示した。同知事は、2011年度から池田市、豊中市など3市2町を一つの「広域連合」として、そこに教員人事権を移譲することを表明している。実現すれば、教員は原則として採用された地域の中でのみ勤務することになり、他の市町村に異動することはない。まさに地域に密着した教員になるわけで、これは学校現場の在り方だけでなく、教員、子ども・保護者、地域住民との関係にも大きな影響を及ぼすことは間違いないだろう。
市町村への教員人事権の移譲は、地方分権、地域主体の教育改革という現在の流れに沿ったものであり、保護者など一般の人々の間でも歓迎する声が多い。では、大阪府に続いてほかの都道府県も教員人事権の移譲に乗り出すかというと、そうでもないようだ。というのも、教員人事権の移譲については、教育関係や教育委員会団体などの間で意見が分かれているからだ。
これまでは調整がつかず棚上げに
じつは、教員人事権の移譲は、文科省がかねてから検討していた課題だった。中央教育審議会は2005年10月、答申「新しい時代の義務教育を創造する」の中で、将来的に市町村に教員人事権を移譲する方針を打ち出し、当面は人口30万人以上の中核市に対して人事権を移譲することを提言した。ところが、教員の広域人事ができないと義務教育の質に地域格差が生まれるという理由で、都道府県教委団体が反対。加えて、人事権の受け皿となるはずの市町村でも、教員給与など財政負担の増加を懸念した町村教育長会が反対に回り、結局、賛成したのは政令指定都市と中核市の教委団体のみだったという経緯がある。
これに対して文科省は、中核市への教員人事権の移譲を目指して、教委関係者らから成る「県費負担教員の人事権等の在り方に関する協議会」を設置し、具体的な課題と対応について、意見交換を行うなどしたが、提言などは出されていない。橋下知事の要請を受けて、鈴木副大臣が人事権移譲の方針を即断した背景には、さまざまな政治的思惑もあろうが、政権交代がなければ実現はやはり難しかっただろう。
実際、教育関係者の間では、市町村に教員人事権を移譲すると、教員採用で都市部などに応募者が集中し、教員の質に地域格差が生まれると懸念する声が多い。また、一つ自治体に定年まで勤務することになれば、人事の停滞によるモラル低下や、さまざまなしがらみが生まれるなどの弊害を指摘する意見もある。橋下知事が5市2町による広域連合を人事権移譲の受け皿にしようとしているのも、一定規模の人事異動を維持するためのものだろう。
自治体間に競争原理を持ち込む可能性も
市町村への教員人事権の移譲に関する課題は先に幾つか述べた。だが、最大の課題は、教員給与などの財政問題だ。市町村への人事権移譲を認めた文科省も、給与財源となる義務教育費国庫負担金まで移譲することは現行では不可能という見解を示している。これに対して鈴木副大臣は、義務教育費国庫負担金をほかの補助金と併せて「教育一括交付金」として市町村に配るアイデアを示している。民主党を中心とする新政権の姿勢を見る限り、おそらくこの方向で議論が進むと思われる。
確かに、教員給与などの財源である義務教育費国庫負担金を「教育一括交付金」として都道府県から市町村に移せば、形式的には財源問題は解決できる。だが、現実には多くの問題が残る。現在、公立小・中学校教員の給与は、国が3分の1、都道府県が3分の2を負担しており、都道府県にはそれに見合う分の地方交付税が措置されている。ところが、地方交付税の使い方は自治体の裁量にゆだねられている。つまり、国が教育一括交付金として教員給与の3分の1を措置しても、残りの自治体負担分は地方交付税として措置されることになるため、それが全額教員給与に充てられるという保証はないのだ。
たとえば、財政力の低い自治体では教員の給与や手当を低く抑えようとするだろう。また、正規教員を採用する代わりに、非常勤講師や期限付き採用教員など充てて人件費を抑制しようという自治体も出るだろう。現在でもこのような動きは、一部の都道府県で既に見られる。そうなると、財政力のある自治体は有利な条件で優秀な教員を集め、財政力の低い自治体は正規教員の確保さえおぼつかないという事態が起こる可能性は十分にあり得る。言い換えれば、市町村への教員人事権の移譲は、教員採用などにおいて自治体間に競争原理を持ち込むことだと言ってもよい。そして、それは自治体間で義務教育の質に格差が生まれることを意味している。
格差は自治体の自己責任として地域と共に生きる教員を選ぶのか、それとも都道府県全体で義務教育の質を均等に保つための教員を選ぶのか。都道府県から市町村への公立小・中学校教員の人事権移譲は、単に地方分権や地方教育行政の議論にとどまらず、日本の義務教育の在り方そのものを問う問題を内包していると言える。

斎藤剛史(さいとう たけふみ)
1958年、茨城県生まれ。法政大学法学部卒。日本教育新聞社に記者として入社後、東京都教育庁、旧文部省などを担当。「週刊教育資料」編集部長を経て、1998年に退社し、フリーのライター兼編集者となる。現在、教育行財政を中心に文部科学省、学校現場などを幅広く取材し、「内外教育」(時事通信社)など教育雑誌を中心に執筆活動をしている。ブログ「教育ニュース観察日記」は、更新が途切れがちながらマニアックで偏った内容が一部から好評を博している。
構成・文:斎藤剛史
※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。
ご意見・ご要望、お待ちしています!
この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)
「教育トレンド」の最新記事














 教育インタビュー
教育インタビュー 新刊紹介
新刊紹介 教材紹介
教材紹介



 この記事をクリップ
この記事をクリップ クリップした記事
クリップした記事 ご意見・ご要望
ご意見・ご要望
